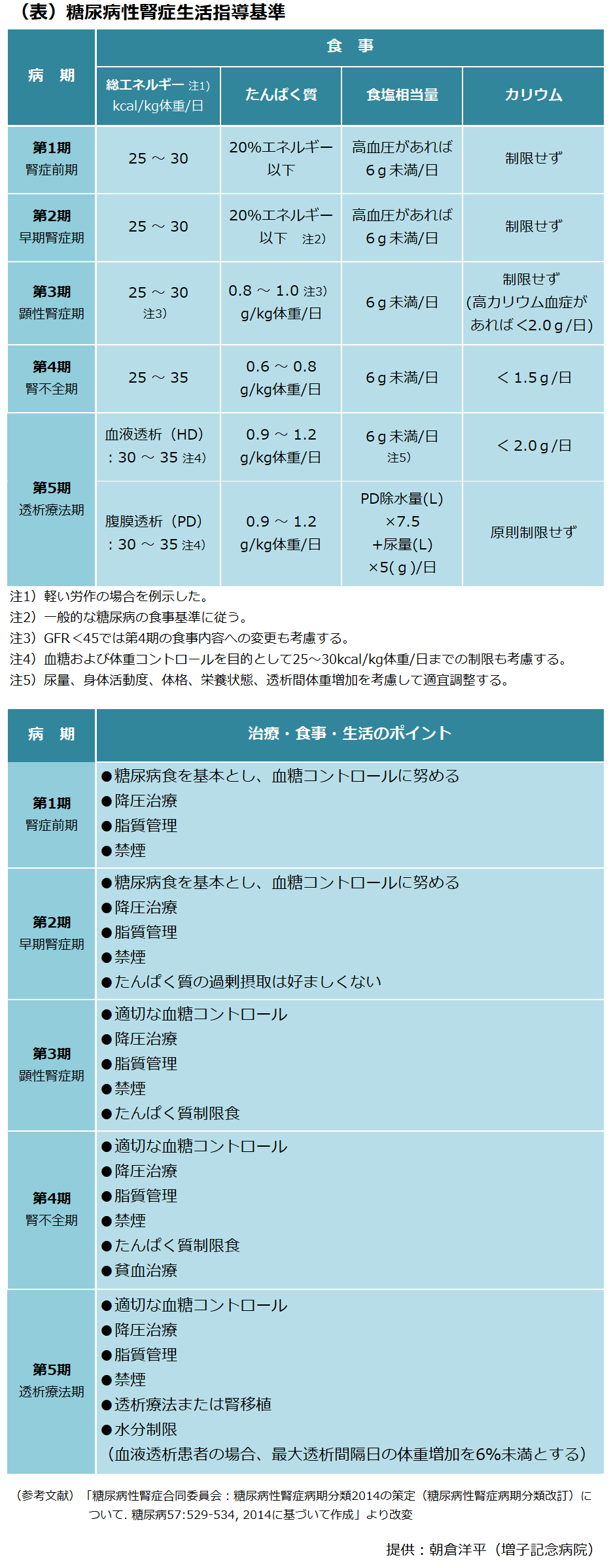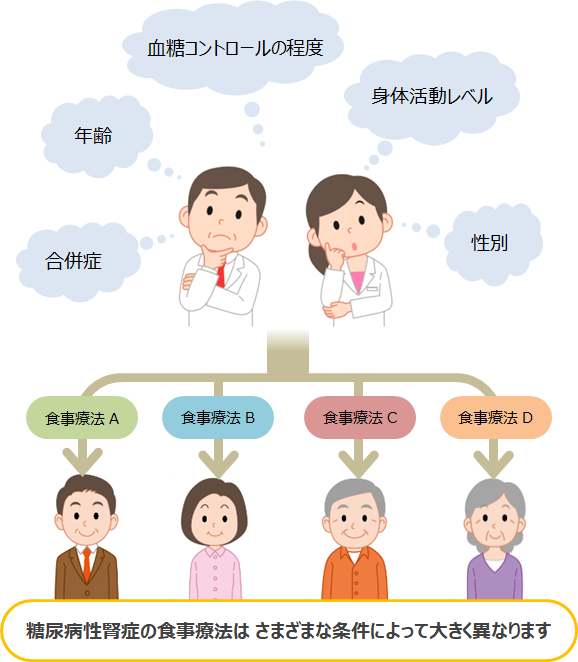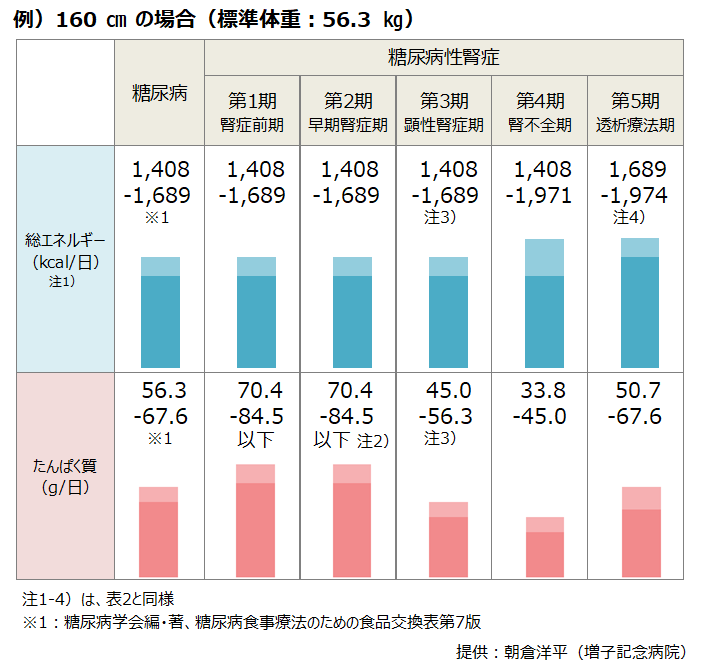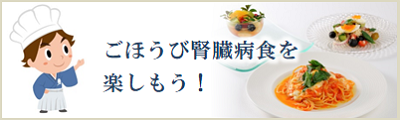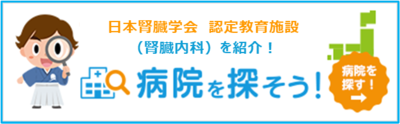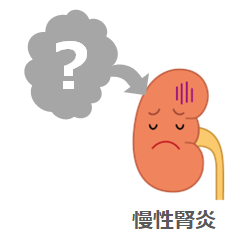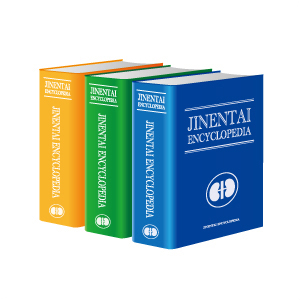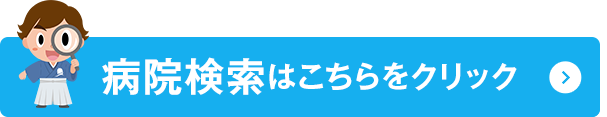慢性腎臓病を治療するためには
どのような病院を受診すればいいですか?
どのような病院を受診すればいいですか?
慢性腎臓病を治療するためには
どのような病院を受診すればいいですか?
どのような病院を受診すればいいですか?
名古屋大学 大学院医学系研究科 病態内科学講座 腎臓内科学 教授 丸山 彰一 先生
名古屋大学 大学院医学系研究科 病態内科学講座
腎臓内科学 教授 丸山 彰一 先生
腎臓内科学 教授 丸山 彰一 先生
2017.07.20 教えて!ドクター



 ・糖尿病食:控えめ
・糖尿病食:控えめ ・糖尿病食:適正に(高血圧があれば、制限)
・糖尿病食:適正に(高血圧があれば、制限) ・糖尿病食:適切に
・糖尿病食:適切に ・糖尿病食:制限なし
・糖尿病食:制限なし