☞ 「病院を探そう!」日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院のご紹介ページ
生着期間や生存期間に影響する因子
<免疫学的要因>
生着期間や生存期間に影響する因子はたくさんあります。免疫学的なこととして、拒絶反応を起こさないようにすることは重要です。抗HLA抗体陽性移植が増えてきているので注意も必要なのですが、免疫抑制薬の進歩により、移植後3か月以内に起こることが多い急性拒絶反応は少なくなってきています。しかし、急性期を問題なく経過しても、移植腎はレシピエントにとって自分のものではないので、拒絶反応を起こさないために免疫抑制薬をきちんと内服し続けなければいけません。感染症などにかかって免疫抑制薬を減量する期間が長い時や怠薬などにより、慢性期にも拒絶反応を起こすことがあります。移植前に感染症の評価やワクチン接種をするのは、移植後のそうしたリスクを少なくするためです。
<その他の要因>
拒絶反応以外の非免疫学的なこととしては、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満、喫煙などの生活習慣病関連のリスク因子があります。これらの管理が悪いと、移植腎への負担は大きくなり、生着期間は短くなります。腎機能が早期に低下することにより、生存期間も短くなります。
また、これらのリスク因子により心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患を発症しやすくなります。心血管疾患、感染症、癌はdeath with function(移植腎は機能しているものの、他の原因で死亡すること)の3大原因です。以下はアメリカのデータですが、拒絶反応などで移植した腎臓の機能を失い、透析再導入になる人や再び移植を受ける人の割合は減少してきているのに対して、death with functionの割合はあまり変わっていません(*)。
移植患者さんにしていただきたいこと
生着期間、生存期間を少しでも長くするために、移植医もレシピエント自身もやらないといけないことがあります。レシピエントができることとしては大きく2つあります。1つは、免疫抑制薬をきちんと内服することです。移植から間もないときは、免疫抑制薬を飲み忘れたりすることは少ないですが、生着年数が長くなると、ちょっとしたきっかけから飲み忘れが始まることがあります。長く生着しても移植された腎臓はもともと自分のものではありません。免疫抑制薬を飲み忘れることにより、ドナーに対する抗体が作られます。その抗体は、ゆっくり腎臓を攻撃していきます。後悔して飲み忘れを直しても、いったん出来上がった抗体による拒絶反応を治療するのは、免疫抑制薬が進歩した近年でもとても難しいのです。
☞ 参考:腎移植ライフ「腎移植後の服薬」
2つ目は体重の管理です。移植後は食事制限もなくなり、ステロイドによる食欲増進も手伝って過食になりがちです。体重増加は血圧、血糖、脂質上昇に大きくかかわっています。食事が美味しく食べられることは、移植後の経過が良いことの証明でもあります。しかし一方で、その腎機能を少しでも長く維持するために、美味しいものを楽しんだ後は、体重測定をきちんとしながら体重増加しないように努力することが必要です。
☞ 参考:腎移植ライフ「腎移植後の食事」「腎移植後の運動」
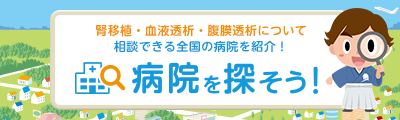
☞ 「病院を探そう!」日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院のご紹介ページ
<出典>
* United States Renal Data System 2013 USRDS Annual Data Report vol.2:290






