
2025.02.28 慢性腎臓病患者インタビュー
慢性腎臓病患者インタビュー

Chapter 4: 厳しい診断結果。もっと早くに腎生検を受けていれば...
----- 腎生検の結果は、いつ、どのように伝えられたのですか。
堀さん:
退院の数日後、主治医の先生から、結果説明の日程調整のお電話をいただきました。その際、先生から「もし事前にネットで調べるなら、膜性腎症ではなく、IgA腎症を調べてください」と言われました。調べてみると、透析導入原因の多くを占める病気※と書かれていて、これはちょっと大変だなと思いました。「透析」という言葉が他人事ではなくなった瞬間でした。ただ、むくみ以外に症状は無いし、腎臓の機能を示すクレアチニンの値も正常だったので、自分はまだそこまで深刻な状況ではないだろうと思っていました。
※透析患者さんの導入原疾患のうち、IgA腎症に代表される慢性糸球体腎炎は、2010年末時点で36.2%と最も多く、2022年末時点でも24.0%を占める(*1)。
退院して10日くらい後、主人と一緒に大学病院に行って、主治医の先生から結果説明を受けました。先生から、改めてIgA腎症との診断結果を聞きました。先生は、腎生検で採取した私の糸球体の写真をたくさん持ってきて、それを見せながら説明してくださいました。採取した37個の糸球体について、一つ一つ「これは駄目」「これは大丈夫」というように評価していき、結果、7割近くの糸球体の機能が失われていました。左側の腎臓から糸球体を採取したので、先生に「右側の腎臓は大丈夫な可能性はありませんか?」とお聞きしたのですが、「残念ながら、右側も恐らく同じ状況だと思います」とのことでした。そして、現時点の症状なども考慮すると、20年後に透析を受けている確率は40%程度であると伝えられました(*2)。
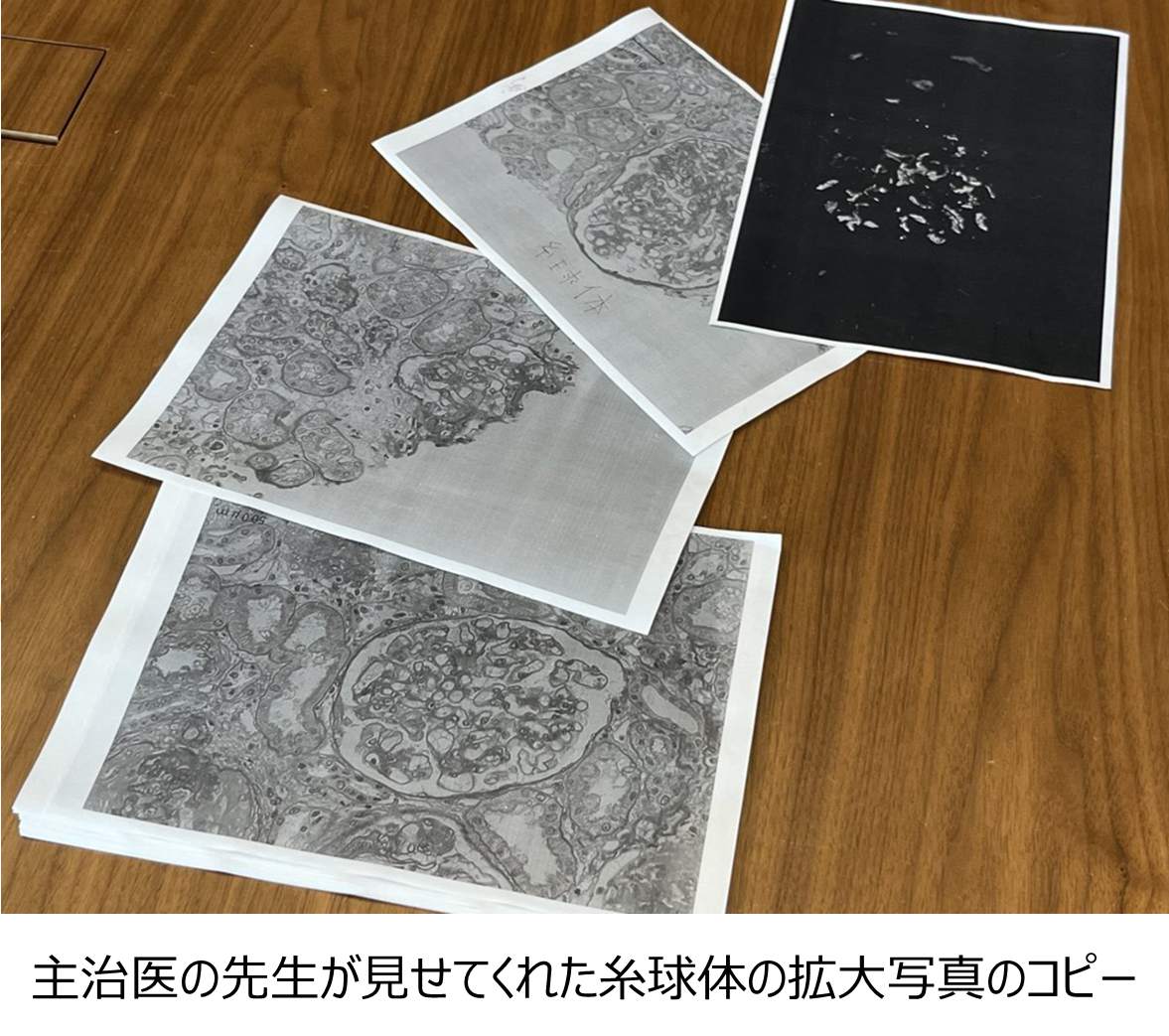
----- 診断を聞いた時は、どのようなお気持ちでしたか。
堀さん:
すごくショックでした。「駄目」と言われるたびに青ざめましたし、どこも痛くないのに糸球体の7割近くがつぶれているという現実を受け入れられませんでした。ただ、自分の腎臓が悪い状態であることを目で見て実感できましたし、先生がはっきり伝えてくれたおかげで、今後の治療に前向きに取り組む覚悟ができました。
----- もっと早くに腎生検を受けていればと思いましたか。
堀さん:
そうですね。そうすれば、こんなに悪くなる前に治療を始められたかもしれないという思いはあります。先生も「もっと早くに腎生検をしてあげれば良かったね」とおっしゃってくださいました。ただ、先生は、最初に見立てた膜性腎症ではなかった場合も考慮した上で、私にできるだけ負担がかからないように腎生検のタイミングを考えてくださったと思いますので、それが影響したとは思っていません。とても話しやすくて、いつも私を気遣ってくれる優しい先生で、すでに転勤されてしまいましたが、心から信頼していました。
それよりも、最初に泌尿器科で検査を受けて異常が見つからなかった時、腎臓内科でも診察を受ける機会があれば、早期診断につながったかもしれないと思っています。
<出典>
*1 花房規男 他. わが国の慢性透析療法の現況(2022 年12月31日現在) 透析会誌2023; 56: 473-536
*2 Koyama A, et al. Natural history and risk factors for immunoglobulin A nephropathy in Japan. Research Group on Progressive Renal Diseases Am J Kidney Dis 1997; 29: 526-32

2025.02.28 慢性腎臓病患者インタビュー

2023.09.29 教えて!ドクター

2024.07.31 教えて!ドクター

2022.03.28 教えて!ドクター